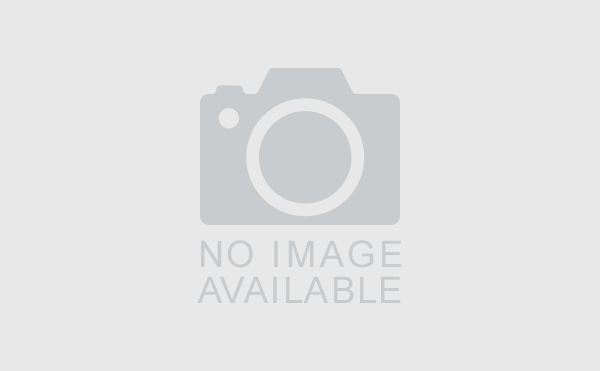民事再生手続において、信用組合の出資金返還債務との相殺が否定された裁判例(大阪高判R5.12.19)
本件(大阪高判R5.12.19)は、再生債務者であるX社がY信用組合に対して出資金の払戻しを請求した事案で、出資金返戻請求権に停止条件が付されている場合において、その返還債権を受働債権とする相殺が民事再生法92条1項によって認められるかが争点となりました。
X社はY信用組合の組合員であり、Yに対して出資金501万円を拠出していました。Xは令和2年1月に民事再生手続開始決定を受け、その後同年9月にYに対し脱退の意思表示をしました。これを受けて、XはYに対し、出資金501万円および遅延損害金の支払を求めて提訴しました。
Xは、出資金返戻請求権は、脱退の効力が発生する事業年度末(令和3年3月末)において組合財産が存在することが令和3年6月の総代会で確認されたことにより停止条件が成就し、請求権が確定したと主張しました。これに対し、Yは、自己が有する貸付金債権(再生債権)を自働債権とし本件出資金返戻請求権を受働債権として相殺した旨を主張しました。すなわち、Yは「停止条件不成就の利益を放棄した」として、民事再生法92条1項に基づき相殺が許容されると主張したのです。
第一審は「民事再生法92条1項の趣旨に鑑みれば、同項により再生債権者がすることが許される相殺における受働債権に係る債務は、再生手続開始当時少なくとも現実化しているものである必要があり、将来の債務など当該時点で発生が未確定な債務は、特段の定めがない限り、含まれないと解することが相当である。」として、出資金返戻請求権は組合脱退の効力が発生する事業年度末時点で初めて成立する停止条件付債権であり、民事再生手続開始時点(令和2年1月)では現実化していなかったため、同法92条1項の「債務」には該当せず、相殺は許容されないとしました。
本判決も第一審を支持し、控訴を棄却しました。高裁は、「未成就停止条件付債務は、再生手続開始当時において、民事再生法92条1項にいう『債務』に該当しない」と明確に説示しています。また、信用組合側が「停止条件不成就の利益を放棄した」としても、それによって法92条1項が要求する債務の現実性が補完されることはないとされました。
この判例から導かれる実務上のポイントは、以下のとおりです。
- 民事再生手続開始時点で未だ発生していない停止条件付債務(例:出資金返戻債務)は、再生債権者の相殺において「債務」として取り扱われない。
- 条件不成就の利益を債務者が一方的に放棄したとしても、そのことによって92条1項に基づく相殺の要件を満たすとは解されない。
- 出資金返戻請求権のように、一定の組合内手続(総代会での財産確認など)を要する債権については、債務の発生時期に十分留意する必要がある。
同じ倒産法でも、破産法67条2項は停止条件付債務の相殺を認めています。倒産の種類によって、結論が異なるのはやや奇異に感じるかもしれませんが、再建型手続と清算型手続の目的の違いから生じるものと考えられます。こういうところが法律の面白いところであり、難しいところです。
もっと詳しく知りたい→民事再生手続における、相殺の規律(相殺禁止の範囲や、相殺に対する対応)については、こちらのサイトをご参照ください。